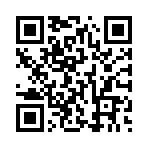› 白くまのほのぼの日記 (アルビノと共に生きる) › 講義アルビノ・誰のせいでもない
› 白くまのほのぼの日記 (アルビノと共に生きる) › 講義アルビノ・誰のせいでもない2010年05月15日
講義アルビノ・誰のせいでもない

講義でも、母の話を通じて、お話をさせていただきました。
私の場合はアルビノ当事者として産まれてきて一度も親を憎んだ事も恨んだ事もありませんでした。
アルビノの場合、両親がアルビノの遺伝子を持っていないとアルビノ子供は産まれてきませんので、私はそのことを知った時に家族が集まっている部屋で「私がアルビノとして産まれてきた事は、誰が悪いとか全然ないからね」と伝えました。
田舎にいきますと、いまだに「ご先祖が昔に悪い事をしたから…」など迷信めいた事を言うところもありますが、それもはっきり言って全然関係ありません。
こういう事が今だに言われるのも、正しい情報がないからなんです。
今回の様な医療関係の学校での当事者による講義はアメリカなど海外では当たり前なんだそうです。
日本でも今後、様々なしょうがいや病気などの当事者が医療関係の学校などで講義できる時代が来る事を願っています。
後半は、石井先生から「楽しい話をしましょう♪」と言ってくださったので、まず私が使用している『補助具』の紹介をしました。
単眼鏡・ルーペなど実際に見て使っていただき、その他の弱視眼鏡や拡大図書機や拡大本の話などしましたら、普段見る事がない補助具に生徒さんは実際に使ってみて楽しんでいました。
単眼鏡は元々は補助具ではありませんが、使い方次第では補助具にもなります。
例えばデジカメも補助具として使う事ができます。
まず見たいものを撮影して液晶画面に写したものを表示して拡大機能で大きくすれば、遠くのものが大きくして見る事ができます。
逆に、いま流行っている『拡大本』は元々、私達の様な弱視の方々に向けて出版されたものですが、いざ出してみますと多くのみなさまが「とても見やすい」と、いまでは当たり前になりました。
こうして相互作用で、うまくいく事も沢山あります。
その他のお話は、私の旅と写真のお話をしました。
活動で巡った全国のお話、初めての海外旅行で行った南極のお話や、その後に行ったオーロラのお話など写真を見せながら、お話をしました。
写真のお話では、私が一度、高校生から20代前半まで使用していた一眼レフカメラを目の病気であきらめ、その後、近年の技術の進歩でカメラに液晶画面がついた事により、あきらめていた一眼レフカメラに再挑戦できたお話をしました。
それは、例え今できない事が、あったとしても「10年後、20年後」にどんな技術が開発されるのか分からない段階で「いまがダメなんだからあきらめなさい!」なんて言ってほしくないと言う事です。
もし夢があるのなら、いまはダメでも将来に向けて挑戦する事の大切さをお話させていただきました。
例えその夢が叶わなくても、挑戦する事、努力する事など大切な事を学ぶ事ができます。
決して無駄ではないんです。
今回はアルビノ当事者の私と出会わせていただいた方々の話しを通じて、生徒さんは何かを感じて下さった事でしょう。
この経験が医療現場に出た際に少しでもやくにたっていただけたらと思います。
そして、今後アルビノやその他のしょうがいや病気などへの理解のある医療従事者が、ひとりでもふたりでも増えていただける事を願います。
Posted by 白くま at 07:50│Comments(0)